こんにちは。
夏休みの終盤、息子が受けた「筑駒力診断」の結果が返ってきました。
👉 過去の記事
【小6受験生】SPICA「筑駒力診断」を受けてきました
8/16にテストを受けて、8/22には郵送で届きました。
8/23から順次郵送という案内だったので、早く届きましたね。
実際にどんな診断が返ってきて、どう受け止めたのかをまとめてみたいと思います。
結果の内容
今回の受験者は80人。
算数はやや平均を下回りましたが、その他の教科は平均以上。
総合では80人中18位という結果でした。
予想以上の出来です。
採点は、各教科の担当先生がしてくださっています。
特に印象的だったのは、採点後に返却される「診断書」。
通常模試でもありますが、各分野の理解度が⚪︎・△・×とより細かく整理されていました。
先生からの総合コメントがとても丁寧で具体的でした。
算数では、例えば息子は相似や変化量は⚪︎、面積比→長さの比は×という評価。これもけっこう細かい。
国語については「詩が分からない、難しかった」と本人は話していましたが、診断書では「多少課題は残るものの、現時点では十分対応できている」とのこと。
ただし換言処理に課題が残っていると指摘されていました。
文章を読み替えて理解する力は、筑駒以外の学校でも重要なので今後の課題として意識していく必要がありそうです。
理科や社会のコメントはとても細かく記載してくださっていました。
特に印象に残ったのは理科の溶解度について。
本人が「できなかった」と話していた通り、「情報をうまくまとめられていないので、解法の抜け漏れを確認し、リード文の長い問題に数多く触れること」と具体的なアドバイスが書かれていました。
保護者会でも「筑駒の理科はリード文がとにかく長い」と説明があったので、この指摘はまさに核心だと感じました。
生物分野でも「選択肢を複数すべて選べ」といった問題が出ることもあり、筑駒の理科では読解スピードが求められるのだと実感しました。
一方で、相変わらず得意な社会については、現時点では大きな課題はなさそうな様子です。
ただし今後の時事問題には注視していかないといけないので、秋以降はニュースや新聞からもさらに学びを広げていく必要がありそうです。
息子の筑駒への心境
今回、私が持っている「SPICA」封筒を見た瞬間から、息子は「きた?きた?」とソワソワ。
正直、私としては最近調子のいい息子に対して「良すぎたらどうしようかな…」という心境。
というのも、良い結果を見たら「筑駒を本気で受けたい!」と言い出すのではないかと考えたからです。
夫とも「結果がよかったらその気になっちゃうかな。息子のタイプからすると、筑駒じゃないんじゃないかな。」と話していました。
(狭き門なのはいったん置いといて 笑)
筑駒に強い意欲を持つと、逆に第一志望群の合否に影響してしまわないかと余計な心配をしてしまったのです。
ただ、冷静に考えてみると「本人が行きたいと思う学校にチャレンジする」のが一番大事。
現状では「行きたい」わけではなく、「チャレンジとして筑駒を受けてみたい」という気持ちの段階で、まだまだ目の前の課題に取り組むことに集中しています。
このタイミングで無理に制限をかけるより、本人の意欲を尊重しつつ伴走していこうと思い直しました。
筑駒の特徴(倍率・入試傾向)
そもそも筑駒はどんな学校なのか。
これまで縁のないところだと思っていたのですが、診断結果を読んで改めて考えさせられました。
筑波大学附属駒場中学校(通称・筑駒)は、全国屈指の超難関中学。
定員はわずか約120名で、例年の実質倍率は 5倍前後。
東京御三家(開成・麻布・武蔵)よりもさらに狭き門といわれます。
以前、塾の先生も、筑駒中学入学者は「モンスターレベル」とおっしゃっていました。
入試傾向の大きな特徴は・・・
- 算数:複数分野をまたぐ融合問題が多く、ひらめき力・論理力が同時に試される。
- 国語:随筆や評論に加え、詩や短歌の出題が目立つ。表現を読み替える「換言処理力」が必須。
- 理科:リード文が長く、読解スピードと整理力が問われる。溶解度や生物での複数選択問題も多い。
- 社会:時事問題が豊富。暗記だけでなく背景理解・因果関係を考える力が重要。
つまり「知識を持っているか」ではなく「初めて見る問題をどう解くか」が問われるのが筑駒。
筑駒力診断テストの細かな分析は、この学校に挑むための大きなヒントになると感じました。
今後
今回の結果を受けて、息子はすっかりやる気を見せて、次回筑駒OP模試も受けるそうです。
9月は筑駒OP模試、合不合判定テスト、サピックスOP(開成・筑駒)と模試が立て続けにあり、さらにNN土曜講座・日曜講座で土日祝はすべて埋まってしまいました。
とうとう受験生の秋がやってきた、という感じです。
小学校でも移動教室や学習発表会が予定されており、勉強以外にも行事が多い時期。
夏の疲れも出やすいので、体調管理を第一にしながら、本人が安心して力を出し切れるようにサポートしていきたいと思っています。
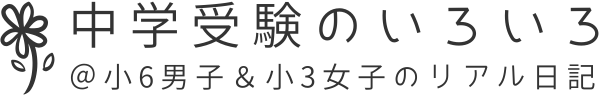

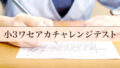

コメント