こんにちは。
9月からは各校の過去問演習が始まり、計画表に沿って取り組んでいますが、開成中については事情が異なります。
NN講座の中で体系的に扱っていくことになっているため、自宅での計画表には入れていません。
塾側での指導方針がはっきり示されているので、それに沿って進める形になります。
初回のNN講座や、日曜講座後のミニ保護者会では、教科ごとに細かい取り組み方が説明されました。
それを整理すると次のようになります。
国語
まず国語については、授業内で過去問演習から解説まで完結します。
自宅で自主的に進めるというよりも、NN講座の流れに乗ることで十分とのことでした。
特に国語は記述量が多く採点の難しい教科なので、塾の解説や添削を受けながら練習することが大切だと感じます。
算数
算数に関しては、ミニ保護者会で詳しい説明がありました。
開成の算数は年度ごとに問題の性質が大きく異なり、「アウトプット型」と「インプット型」の二つに分けて考えるとよいそうです。
- アウトプット型
本番さながらに60分間で一気に解き切る演習。
時間配分を意識し、いかに得点を積み上げられるかを重視。 - インプット型
質の高い問題が多く、学習効果が非常に大きい年度。
まず60分で本気で解答し、その後採点。
すぐには解答解説を見ずに、自力で納得できるまで延長して考え抜くことが推奨。
いわば「教材としての価値が高い年」です。
また、算数では他科目と違い、一度出題された類題は繰り返し出ないという特徴があります。
そのため、ただ10年分すべてを順番に解く必要はなく、むしろ年度ごとの「難度のぶれ」「大問数(3〜5問)の変化」「合格者平均点」などの感覚をつかむことが大事になるとのことでした。
社会
社会は原則として1週間で1年分を演習します。
どの年度を解くかは塾から明確な指示があるので、家庭で迷う必要はありません。
注意点として、古い年度のデータは社会情勢が変わっていてそのまま使えない場合があるそうです。
そのため、過去にさかのぼりすぎる必要はなく、あくまでも「現行の傾向をつかむ」ことが優先されます。
さらに社会では3分野によって難度に偏りがあるようです。
特に地理分野は難易度が高く、逆に歴史と公民は標準的なレベルで出題されることが多いとのこと。
したがって、単なる合計点よりも、分野ごとの得点率をチェックし、弱点を意識して修正していくことが大切だと強調されていました。
理科
理科も基本は社会と同様で、1週間に1年分を扱います。
こちらも「どの年度をいつ解くか」は塾の指示に従って進めていきます。
現時点では理科のミニ保護者会がまだ開かれていないため、詳細な方針は不明ですが、今後改めて具体的な説明がありそうです。
まとめ
こうして見ると、開成の過去問演習は「ただ量をこなす」のではなく、年度ごとの特徴や科目の性質に応じて狙いを持って取り組むことが求められているんですね。
算数は年度の違いを意識してアウトプットとインプットを使い分け、社会は分野別の得点率を重視、理科も塾の指示を待ちながらバランスよく進める。そして国語は塾内完結で対応する。
すべてを家庭で抱え込む必要はなく、塾のカリキュラムに乗ることで効率的に学習を進められるのは心強いと感じました。
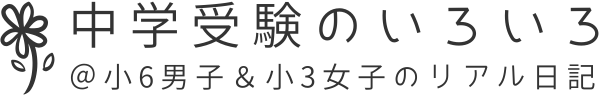
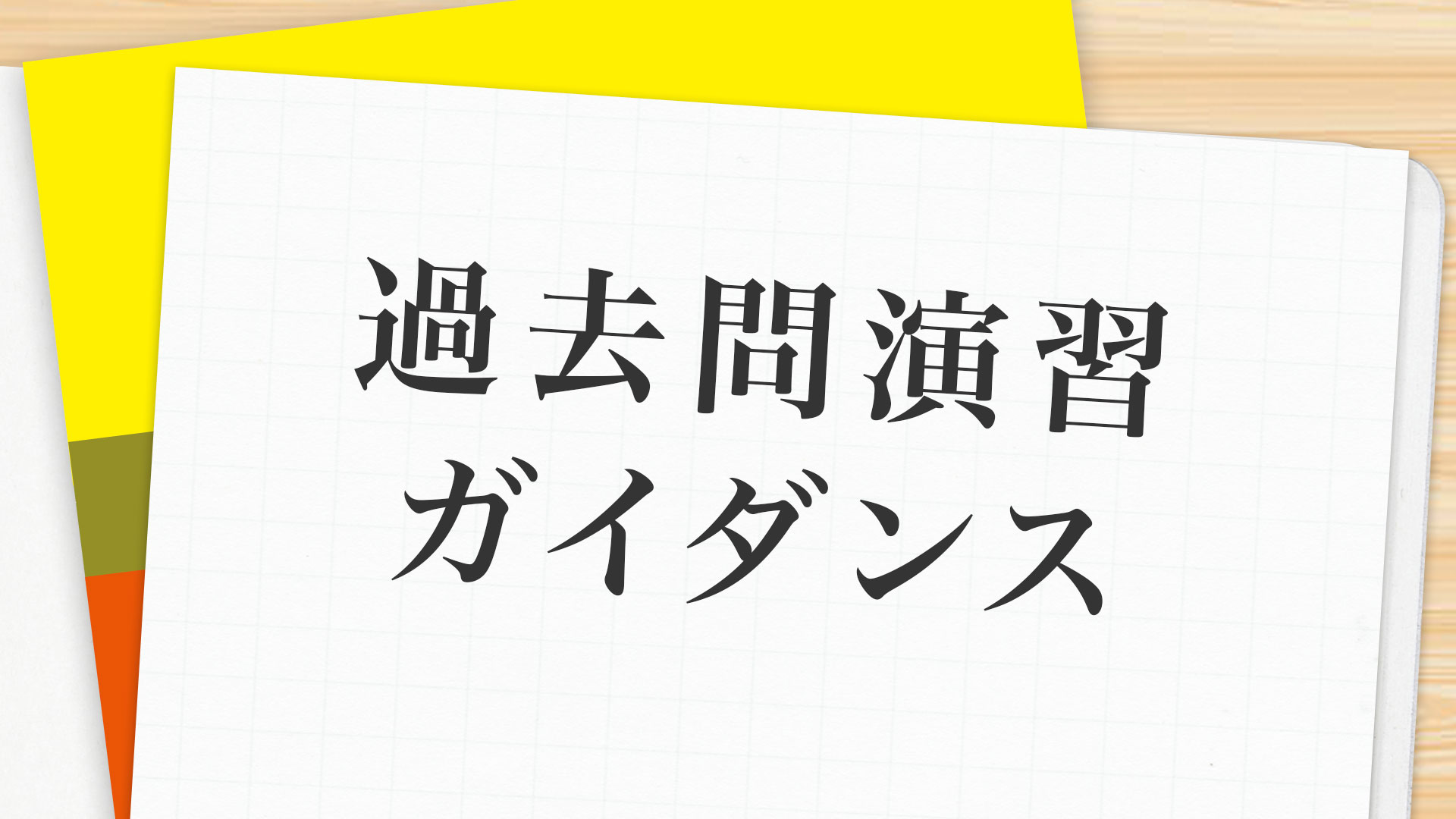


コメント