中学受験生の生活って、どれくらい勉強づくしなの?
学校から帰ってきて、塾にも行くし、いつ家庭学習をすればいいんでしょう?
わが家では、塾に通い出す前から朝の時間を使うようにしています。
今日は、わが家の小6息子(2026受験組)の朝の過ごし方をご紹介します。
特別なことはしていませんが、「無理なく続けられること」が我が家のルールです。
今回紹介するルーティンは、失敗や試行錯誤を経て無理なく続けられるようになった、リアルな習慣です。
朝は6時半起床、学習のスタートは「毎日計算」から
平日の流れを時間に当てはめると、だいたい次のようになります。
- 6:30 起床(冬は6:45になることも…)
起きたらまず着替えて顔を洗います - 6:35〜6:50 算数の「毎日計算」で頭を起こす
- 7:00 朝食
- 7:20 食器洗い・朝の学校準備
- 7:30〜7:50 フリータイム(読書や宿題直しなど)
こうしてリズムを決めておくと、子ども自身が次にやることを考えずに動けるようになり、親の声かけも少なくて済みます。
同様のリズムで過ごしている妹にはまだまだ声かけが必要ですが、息子に関してはここ2〜3年ほとんど私が促すことはないです。
朝食前の学習習慣
今は小6・小3の子供たち。
朝食前の学習習慣は、二人とも小1から始めました。
そのタイミングで良かったと思うのは2点。
小学校に入るという生活が変わるタイミングだったこと。
高学年になると自分で生活リズムを良くも悪くもコントロールできるようになります。その前に朝学習リズムを身につけられたこと。
今では自然に10〜20分程度の朝学習が定着しました。
小1の頃の朝学習は、幼児期から続けているEQWELチャイルドアカデミーの音読や暗唱が中心でした。
起床後は「脳のゴールデンタイム」だそうです。
その時間の音読は、文章理解がはかどり、頭がスッキリとするようです。
眠くてモゴモゴしている日もありますが、それでも声に出しているということでOKと思っています(笑)
その後、音読・暗唱にプラスして計算なども取り組むようになりました。
短時間で取り組める100マス計算などおすすめです。
計算も、頭のウォーミングアップになり脳を活性化させるのに効果的だそうです。
朝食後は兄妹で交代のお皿洗い
勉強とは関係ないですが、朝食が終わったら兄妹で毎日交代制のお皿洗い。
少し気持ちを切り替える時間にもなっているようで、「さぁ学校モード!」という感じに切り替わる瞬間です。
登校前のフリータイムは、宿題 or 読書
お皿洗いの後、登校までは20分ほどのフリータイム。
その時間で、塾の宿題が残っていれば取り組みますし、なければ大好きな読書を楽しんでいます。
朝の時間は「毎日やる」からこそ意味がある
もちろん、最初からうまくいったわけではありません。
特に冬場は起きられず、朝学習ができない日もありました。
そのとき取り入れた工夫が、
- 前夜に机を整えておく
- 前夜に着替えを用意しておく
- 目覚ましをベッドから離れた場所に置く
- 起きたらすぐカーテンを開けて光を浴びる
というシンプルな習慣です。
小さな工夫の積み重ねが、安定した朝のルーティンにつながりました。
朝学習といっても、特別な内容ではありません。
「毎日、同じ時間に、短時間でも机に向かう」——これを続けることで、生活全体にリズムが生まれていると感じます。
今小6になり、塾や模試で忙しい日々は朝がつらい日もあるようですが、
勉強だけでなく新聞や本を読むだけの日もあります。
朝のこの静かな時間が、本人にとっても気持ちを整えるいい時間になっているようです。
まとめ
無理をせず、でも「続ける」ことを大切に。
特別なことはしていないわが家の朝ルーティンですが、毎日の積み重ねが受験勉強の土台になっていると感じています。
おまけ
朝の計算学習で取り組んでよかったのはコチラ。
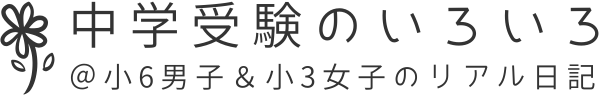



コメント