こんにちは。
先日のマンスリーテストの日に行われた「小3保護者会」に参加しました。
上の兄のときも早稲アカに通っていましたが、兄は小4からの入塾。
そのため、小3のこの時期にどんな話が出るのかは未知の世界です。
しかも、兄妹で性格もタイプもまったく違うので、同じテーマでも私の受け止め方が変わる気がして、保護者会はできるだけ出席するようにしています。
マンスリーテストの位置付けについて
先生からまず伝えられたのは、
「小3・小4は“勉強が好き”でいられることが一番大事です」という言葉でした。
たとえマンスリーテストで点数が取れなくても、
“厳しく注意する必要はまったくありません”とのこと。
この時期は、結果よりも“学ぶことが楽しい”という気持ちをどう育てるかが最優先。
また、テストごとの位置づけも改めて整理してくれました。
- マンスリーテスト:授業で習った内容の「学習成果」を測るテスト
- 全統小テスト・ワセチャレ:応用力・総合力を試す全国模試
つまり、マンスリーテストで点が取れなくても焦らなくていい。
「できなかったところを知る」ことこそ、次につながる大切な学びなんだと感じました。
難関校合格者の小3時点の偏差値
今回、先生が過去の難関中学合格者の小3時点の偏差値を調べたというお話がありました。
開成合格者でも 偏差値51〜70 と幅があり、
「小3で偏差値50あれば十分に狙える位置にいます」とのことでした。
この数字を聞いて、少しホッとした保護者の方も多かったのではないでしょうか。
今は焦らず、基礎をじっくり固める時期なのだと思います。
学習スケジュールの立て方
もう一つ印象に残ったのが「親が全部計画してはいけない」という話。
スケジュールは“親と子が一緒に考え”、子どもが“自分で実行する”形が理想とのこと。
我が家では、私が一方的に計画を立てて娘に渡していたのですが(笑)、
「一緒に相談する」という流れを少しずつ取り入れていこうと思いました。
最初は形だけでも、「どうやってやる?」と聞くだけで、
子どもにとっては“自分で決めた”という実感につながる気がします。
早速一緒に計画を立ててみたところ、最終的なスケジュールは私が作っていたものとほとんど同じになりました。
それでも、「この日に練習問題をやることにする」と一つひとつ自分で決めていく娘の姿は、どこか楽しそう。
作り終えたときには小さな達成感も感じているようで、やはり「自分で決めた」という形にすることはとても大切だなと実感しました。
各教科のポイント
算数
今はとにかく“計算力”をしっかりつけることが最優先。
100マス計算など、スピードと正確さを身につける練習が有効。
また、今後つまずきやすいのは「大きな割り算」や「およその数」「素数」など。
これらを早めに慣らしておくとスムーズだそうです。
図形分野は折り紙や積み木、生活の中では単位換算の感覚を鍛えるのがポイント。
(“このプール何メートル?” “2割引っていくら?”など)
理科
楽しく、身近な“なぜ?”を大事に。
「雲ってなんで浮くんだろう?」などの素朴な疑問を一緒に考え、
興味を持ったら家庭で小さな実験をしてみるのもおすすめとのこと。
国語
小3の今は、音読と四字熟語。
この年齢は、声に出して覚えることで記憶が定着しやすいそうです。
物語文では「内容を理解しているか」を意識して読むことが大切。
社会
授業だけでは定着が難しいので、早稲アカの動画教材などを活用して復習するのが効果的。
わが家の今後の取り組み
娘は最近、算数の「およその数」や「植木算」に苦戦しています。
保護者会で「大きな割り算や素数が大事」と聞き、
早速“素数ドリル”を購入しました。
焦らず、少しずつ、
“できた!”の積み重ねを感じられるようなサポートをしていきたいと思います。
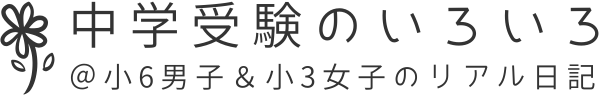
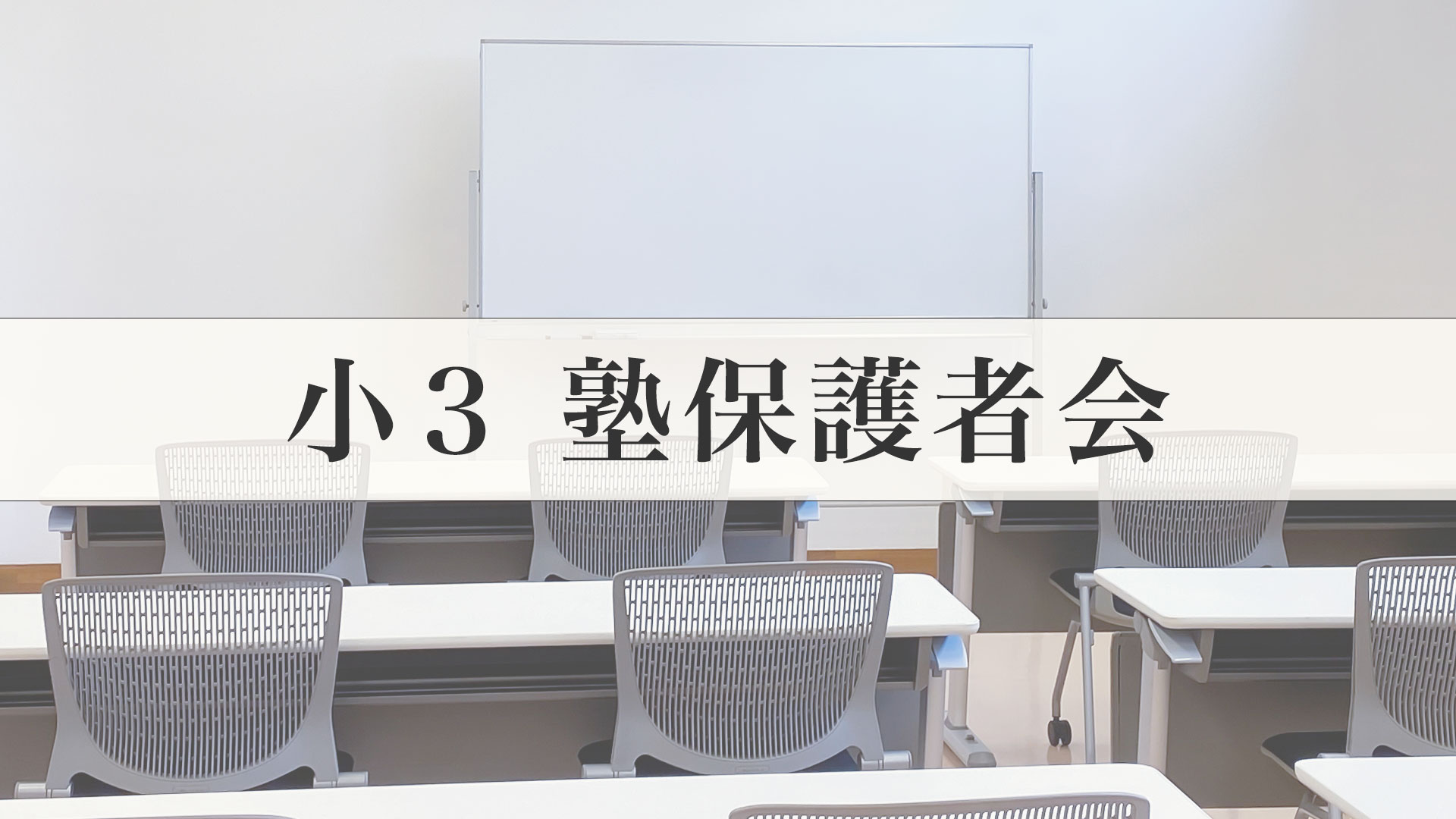
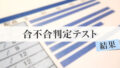

コメント