こんにちは。
NN開成オープン(第3回)後に行われた保護者会での内容の続きです。
これから夏にかけての過ごし方や、秋以降の学習に向けたアドバイスが、教科ごとに詳しくお話がありました。
国語|「質の良い△」を狙う記述力と正確な読解力
記述問題について、まず必要なピースを集めることが大事。
ただ、「必要なピースを集めるだけでは解答にはならない」とのこと。
大切なのは、それらピースを論理的に組み立てる力。
また、記述で「◯」はほぼもらえない。質の高い「△」を狙うことが現実的な目標だそうです。
また、解法についても「知っている」だけでなく、それを使いこなす段階まで引き上げる必要があるとのこと。
特に夏は、この“使いこなす”=実践を磨く重要な期間です。
我が家でも、以前から気になっていた国語の「スピード」問題。
👉【小6受験生】国語の読解スピードを上げたい|時間を意識した学習とタイマー活用
これはよく7・8・9月くらいに相談があるそうです。(うちだけではなかった・・・)
ただ、現状ではスピード以上に正答率を上げ、正確に読み解く力を上げることのほうが重要とのこと。それがあれば、自然と理解と実践のスピードが上がるそうで、12・1月にはそのような相談がほぼないそうです。
とはいえ、スピードを全く意識しないのもどうなんだろう?と思っていたら、息子の方から提案が。
「NNのような難しい問題では正確に読み解くことを意識して、校舎の授業で扱う問題ではスピードを意識しようと思うよ」
自分なりのバランスを考えているようです。
なるほど、それでいきましょう。
社会|知識の穴を埋め、引き出しを増やす夏
この夏は、社会の知識の穴を埋めましょう。
量と質、どちらが大事か?という問いには「量」との答え。
なぜなら量をこなせるのはこの時期が最後だから。
秋以降に「質」を高めるためにも、今のうちにインプット量を増やすことが重要だそうです。
また、暗記の仕方もポイントで、
- 単語だけを断片的に覚えるのではなく、
- 複数の情報を「組み合わせて」覚えること
これにより、情報を引き出しやすくなるのです。
とにかく「引き出し」を多く持つこと。
秋からは、夏までにインプットした情報をアウトプットしていく時期です。
最難関校では初見問題も多く、知っている情報をどう組み合わせるかが勝負です。
増やした“引き出し”から、推測して解いていく「類推力」を強化していくそうです。
理科|70点満点のうち「20点」をどう取るか
理科は、NN後期講座で網羅するため50点分は比較的取りやすいとのこと。
難しいのは残り20点。ここは初見対応力・分析力が問われます。
夏にやるべき具体的な対策:
- 知識の強化:植物・昆虫・気体・水溶液などを完璧に
- 化学分野の基本解法を確実に身につける:溶解度・気体・中和・燃焼
夏にやるべき具体的な対策:
- 分類と実験器具について対策
※開成は「実験器具」がとにかく難しいそうです - 天体・力学は秋以降に本格対策
- 天体のキーは「太陽」
- 力学は「てこ」
また、設問者の意図を読み取る力が問われる場面もあり、夏期集中特訓では「処理力」と「精度」を上げるトレーニングが中心になります。
算数|「攻める夏」、量より質の学びへ
得意でも、苦手でも、とにかく「攻める夏」という話がメインでした。
算数に弱点を抱えている子は、もちろん「守る」ことも必要ですが、基本をやるにしてもある一定レベルを担保すること。
「ある一定レベル」というのはなかなかマルがつかない教材。正解しなくてもいいんです。
「量」より「質」の学習で算数の能力を高めることが何より大切。
反復をする「偏差値を上げる」学習というのは「アウトプット訓練」。
これは100の力を持っていたら、100出せることを目的とした学習。
「能力を高める」=量より質を高めるのは「インプット訓練」。
これは、100の力を110、120へ高めていく学習。
夏〜11月までは「インプット訓練」が大事だそうです。
なので、NNでの算数は復習不要。
初見問題に対して、どの解法でいくのか最短ツールをジャッジする訓練をします。
最近算数のミスが多い息子。
👉 前回のNN開成オープンレポートはこちら
息子とはミスをどう減らすか、話し合いを重ねてきました。
ただ、今回の話では「今は計算ミスは気にしすぎなくていい」との意見もあり、ちょっと判断に迷っています。
息子の場合は計算というより“解法選択ミス”が多い印象なので、その部分は見過ごさず対応していった方がいいのでは?と思っています。
次回保護者会のテーマと今後について
次回のNN開成オープンに合わせた保護者会では、
- 模試ラッシュの詳細
- 秋以降の本格的な学習計画
- 過去問の取り組み方
について詳しくお話があるようです。
いよいよ秋本番に向けて、受験生活も加速していきますね。
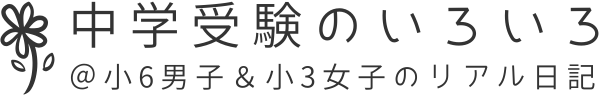
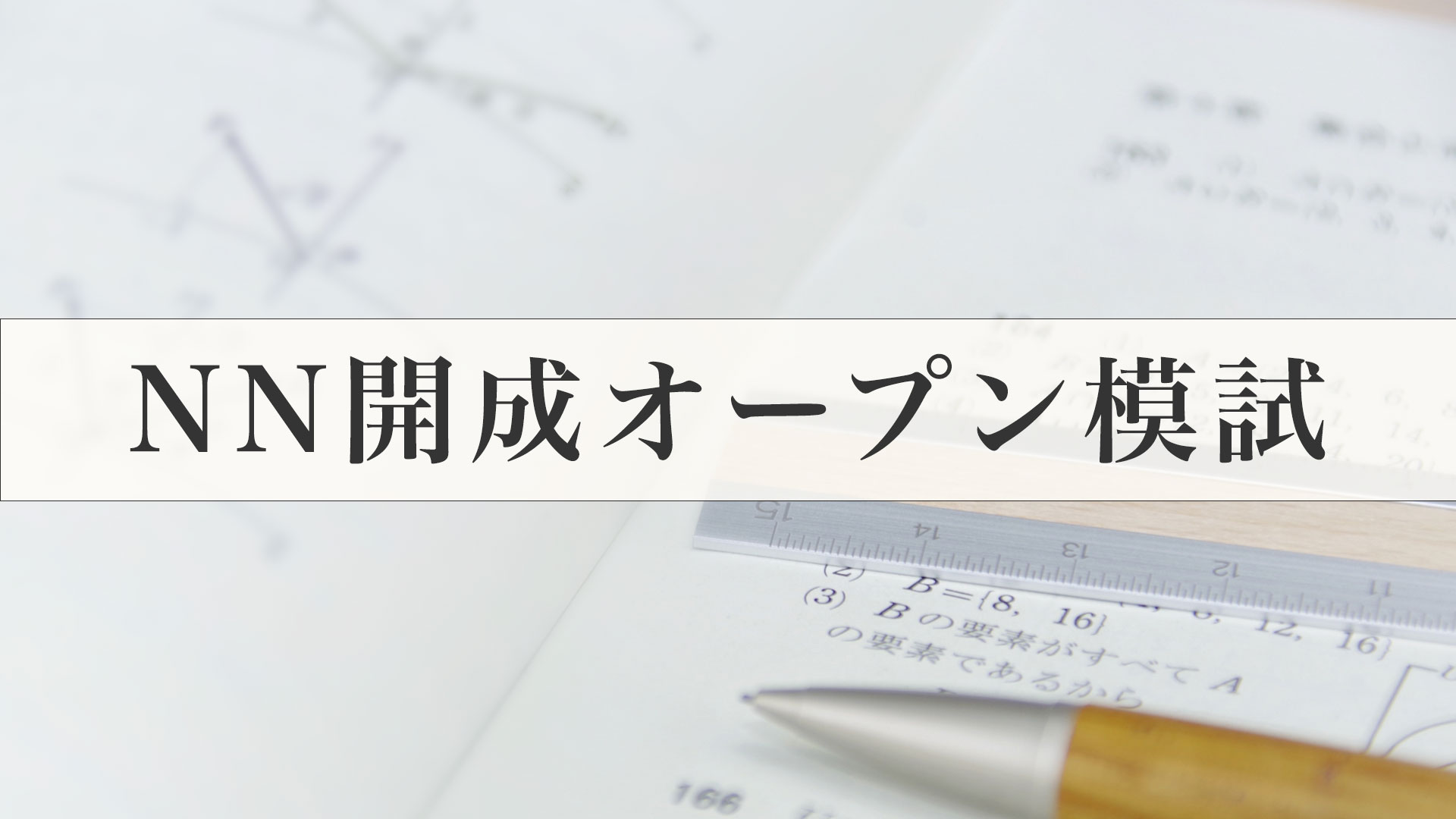


コメント