こんにちは。
今回はミスに関するお話です。
先日のNN開成オープン模試の算数で、息子がまさかの30点分のミス。
その時の記事はこちら
👉【小6早稲アカ生】NN開成オープン模試 第2回 気になる手応えと今後の動き
👉【小6早稲アカ生】NN開成オープン模試 第2回 結果がでました
先日のミニ保護者会で先生が、算数の点数での筑駒合格圏の話をされていて、それに照らし合わせると30点で「合格安全圏」から「挑戦圏外」へと転落した計算に。
ミスの重みを、数字で改めて突きつけられました。
当然ながら、次回はこの“もったいない”ミスを減らしたい。
そこで、息子と一緒に振り返りをしていると…
私「なんでミスしたと思う?」
息子「うーん、⚪︎⚪︎を◻︎◻︎って勘違いしちゃってさ」
私「なんで勘違いしちゃったんだろう?」
・
・
・
そんな会話をしていたら、隣で聞いていた夫が「それってトヨタの5Why(ファイブ・ホワイ)じゃん」と一言。
「トヨタ式5Why」って?
「なぜ?」を5回繰り返して問題の本質にたどりつく、というシンプルかつ効果的な分析法。
トヨタ自動車の生産現場で生まれた問題解決の技術で、ビジネスの世界ではとても有名なフレームワークだそうです。
実は私、その話は全く知らなかったのですが、最近娘のミスに対してこの5Whyを無意識に実践していたのです!
こんな感じで:
〈娘のミス例〉
「なんで間違えたんだろう?」
→「3を8って書いちゃったから」
→「なんで3を8って書いちゃったの?」
→「筆算の文字が重なってたから8に見えた」
→「なんで文字が重なるところに書いたの?」
→「スペースがそこしかなかったから」
→「じゃあ、次からはノートに余裕を持って書こっか」
こんなふうに、ただ「気をつけてね」で済ませずに深掘りしていくことで、次に具体的にどう気をつけるかが見えてきます。
※もちろん必ず「5回」とは限りません。具体的な要因が見えてくればOK。
息子のミスも「次に活かす」ステップへ
息子の方も、5Whyの手法で振り返ってみたところ、「⚪︎⚪︎な問題文の読み方に引っかかっていた」ことがわかりました。
具体的改善策の例
- 模試や過去問では、最初に「解く順番」を決める
- 1問にかける時間を意識して、時計を使いながら解く
- 計算問題は最後に見直す時間を残す
この工夫を取り入れることで、同じタイプのケアレスミスはかなり減ってきました。
数字だけでなく、ノートの書き方や時間配分など、具体的な改善ポイントが見えてくるのがポイントです。
「ミスを減らそう」より「何に気をつけるか」
中学受験では、ミスの積み重ねが命取りになることも。
でも、「ミスを減らす」だけでは子どもにとって抽象的すぎて動きづらい。
「⚪︎⚪︎のときに注意する」「ノートの書き方を変える」など、具体的なアクションに落とし込むことが、最終的に“減点回避”につながっていくのだと改めて感じました。
まとめ
ケアレスミスは、単なる注意不足ではなく、原因を整理して改善策を作ることが大事です。
「5回のなぜ?」を使うと、漠然とした反省が、次回の行動に直結する学びに変わります。
模試や過去問のあと、ぜひ親子で一緒に「なぜ?」を繰り返してみてください。
小さな工夫の積み重ねが、受験勉強の質をぐっと高めるのかなと思います。
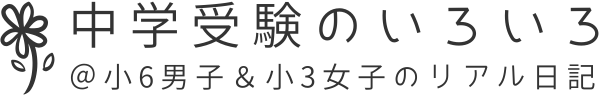



コメント