こんにちは
塾に入ってテストを受けるたびに出てくる数値について。
中学受験の話題で必ず出てくる「偏差値」。
塾の先生も、模試の結果も、学校の目安も、すべてこの数字を中心に語られます。
でも、本当のところ偏差値って何を意味しているのでしょうか?
みなさんには当然のように知っていることかもしれませんが、偏差値の基本からわが家での活用方法までを、私なりの理解でまとめました。
偏差値とは何か?
偏差値とは、「ある集団の中で自分がどの位置にいるか」を示す相対的な数値です。
平均点を偏差値50とし、そこからどれくらい高いか低いかを数値で表しています。
つまり、同じテストでも受験者層が違えば偏差値も変わります。
絶対的な学力を示すものではない、という点がポイントです。
偏差値の計算方法(簡単に)
厳密には「(自分の得点 − 平均点)÷ 標準偏差 × 10 + 50」という計算式で算出されますが、日常ではあまり気にしなくても大丈夫なようです。
偏差値の分布イメージとしては
- 偏差値70:全国でもトップ層(上位2%)
- 偏差値60:上位16%
- 偏差値50:ちょうど真ん中(平均)
- 偏差値40:下位16%
といった具合。つまり、偏差値60というのはかなり優秀な成績だということになります。
「どのくらいできているか」だけでなく「相対的に自分がどこにいるのか」を知るツールと考えると分かりやすいです。
中学受験での偏差値の見方
平均点を使った計算で出されるので、模試の難易度や受験者層によって、偏差値の出方が変わってきます。
- 四谷大塚(合不合判定テスト):広く一般的な基準。受験者層も幅広い。
- 早稲田アカデミー(NNオープンなど):志望校別、上位層中心。
- SAPIX(サピックスオープン):非常に難易度が高く、偏差値が取りにくい。
たとえば同じ子でも、「合不合で偏差値60、NNオープンでは52、サピックスオープンでは48」なんてことも珍しくないそうです。
それぞれの模試の特性を理解しておくことが大切です。
偏差値の落とし穴
偏差値は便利な指標ではありますが、万能ではありません。
以下の点には注意が必要です。
- 模試の難易度や受験者層で大きく変わる
- 科目ごとの偏差値に差が出やすい(算数だけ高い、など)
- 一度の偏差値で一喜一憂すると疲れてしまう
特に模試のたびに上がった下がったと振り回されるのは避けたいところです。
わが家の場合:息子・娘の偏差値推移
息子の場合、小4から早稲アカで通塾スタートしましたが、最初の頃は毎回偏差値にかなりバラつきがありました。
小5の後半から、かなり安定してきましたが、それでも模試の種類によって多少バラつきがあるのが正直なところ。
小5終わりころに「開成・渋幕を第一志望にするなら、組分けテストか志望校判定模試などで一度は偏差値70を超えておきたい」と塾の先生からは言われました。
これも一つの基準になりそうです。
息子は、小5の1月の志望校判定と小6の4月の合不合判定模試(B特待認定!)で超えることができました。
関連記事 👉【小6早稲アカ生】小6春、合不合でB特待に!早稲アカの特待制度について
ちなみに、小6最初のNNオープン模試の結果はこちら
- NN開成オープン模試… 偏差値 65.2
- NN渋幕オープン模試… 偏差値 52.5
開成オープン模試(開成そっくりテスト)やNN開成講座を小5のときに受けているので、開成問題には慣れていて、渋幕オープン模試(渋幕そっくりテスト)に慣れていなかったようです。
なのでテストとの相性も大きく関わってきますね。
娘は現在小3ですが、全統小(=全国統一小学生テスト)を一度受けましたが、
一問一問どんな間違いなのか、見直す必要があるか、などに焦点をあてて確認し、まだ偏差値は注視しないようにしています。
いずれ模試を受けるようになったら、偏差値はイチ基準であることを伝えていきたいです。
まとめ:偏差値は参考資料、すべてではない
偏差値は中学受験において大切な指標ですが、それ自体に一喜一憂するのではなく、
- 現在の学習状況を知る
- 志望校選びの参考にする
- 今後の学習計画を立てる
ために「道具」として活用することが重要です。
偏差値は便利な「ものさし」ではありますが、それだけにとらわれない視点も大切です。
子どもにとってはあくまで一時的な数字であり、何を理解していて何が分かっていないか、そして最終的には合格できる力があるかどうかが大事だと思います。
親としては冷静に、必要なら戦略的にこの数字と向き合い、子どもには前向きな声かけをしていきたいですね。
ここは私の課題でもあります。
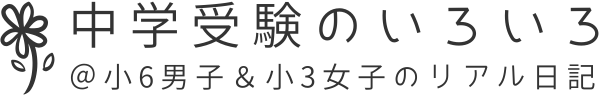



コメント